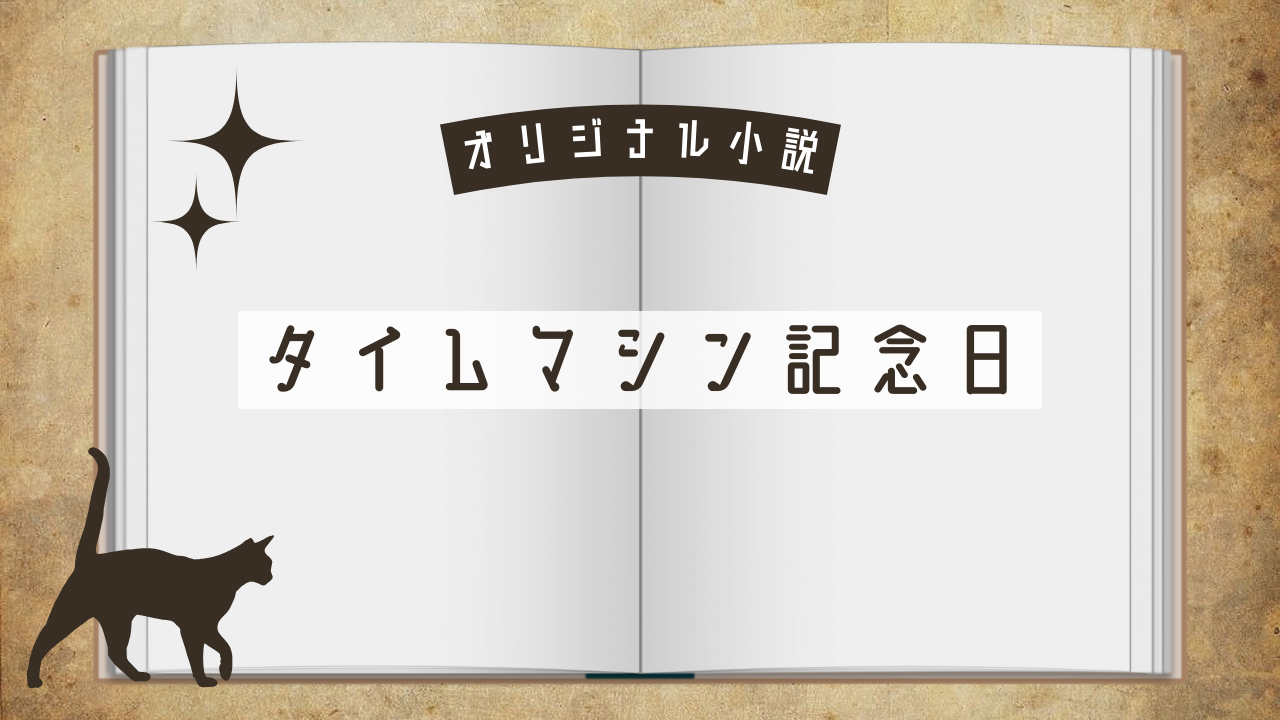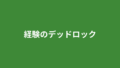あるところに、タイムマシンの開発に人生を捧げた男がいた。
彼は類まれなる才能を持ち、タイムマシンを完成させられるのは彼しかいないと言われていた。
最近、開発が進み、彼はさらに研究に没頭していた。人生のすべてを捧げる覚悟で、愛する恋人とも開発をめぐって喧嘩別れしたほどだった。
彼の覚悟を固めさせたのは、ある装置の完成だった。四畳半ほどのブースのような空間。それは未来から来る者が安全に到着するための「船着場」のような装置だった。
男は、その装置の稼働ボタンを押した。
ランプが点灯し、装置が稼働する。計器の数字を確認すると、すべて男の計算通りだった。
「よし、問題なしだ。」
その瞬間、ガチャリ、と装置のドアが開いた。
中には誰もいなかったはずだ。それなのに、そこから老人が現れた。
男は歓喜した。
「やはり誰か来たか! では、タイムマシンは成功したのだな!」
未来から誰かがやってくる——これは想定内の事態だった。なぜなら、この装置なしでは過去へ行くことはできず、今が最も古い過去になる。ならば、未来人がここに来る可能性は高い。
しかし、男の喜びとは裏腹に、老人は鋭い眼光で男を睨んでいた。
「おい。」
老人は低く言った。
「こんなくだらない装置なんぞ作ってる場合じゃないぞ。」
男は呆気に取られたが、次第に怒りがこみ上げてきた。
「わざわざ未来から来て、一言目が私を愚弄とは。君は一体誰なんだ?」
「何度でも言ってやる。お前は大馬鹿野郎だ。それに、勘も鈍い。まったく嫌になるよ…。いいか、俺は、お前だ。」
「お前が…俺?」
男は絶句した。
確かに未来からやってくるのが自分自身である可能性は考慮していた。しかし、目の前の老人の姿はあまりにも惨めだった。深い皺、窪んだ目、汚れた髪、浮浪者のような服装。
「一体、私の未来に何があったんだ?」
「何も起きていない。」老人は言った。「お前はこのままタイムマシンの研究を続ける。そして、このざまだ。」
「だが、タイムマシンは成功したのだろう?」
「成功はした。だが、実用化には至らなかった。」
老人は左手の腕時計をチラリと見る。それは男の愛用のものと同じだった。
「あぁ、時間がない。俺はすぐに戻らないといけない。」
そう言うと、老人は男の肩を強く掴んだ。
「いいか! 今すぐ研究室を出て、施設の横の花屋で薔薇を買え! そして、少し前に喧嘩別れした彼女にプロポーズしろ!」
男は驚いた。
「なぜそのことを…?」
彼女が好きな花が薔薇であること。そして、彼女と喧嘩してしばらく連絡をとっていなかったこと。
だがすぐに気づく。老人が自分自身なのだから知っていて当然だ。
「そんなことのために来たんじゃないだろう? タイムマシンについて教えてくれ。」
「そんなことのために来たんだよ。」老人は言った。「このままだとお前は今日、彼女を失う。彼女はこの街を出て行ってしまうんだ。そして一生後悔する。」
「タイムマシンの実用化は不可能だ。未来で手に入る燃料を全てかき集めて、俺一人が一瞬ここに来るのが精一杯だった。もう誰もこの装置を使って来ることはない。未来のお前は、死ぬ間際にやっと気づくんだ。タイムマシンより、彼女が大切だったと。」
老人は装置へ戻っていく。
「必ず行けよ!」
そう言い残し、未来へと消えていった。
男は混乱していた。自分の研究が中途半端で終わること。研究より彼女を選べと言われたこと。
男は意固地になった。未来の自分がなんだ。未来の自分が解決できなかった問題も、その原因を知った今の自分なら解決できるかもしれないじゃないか。よしやってやる!そう思った。
だがその時、掃除道具を持った男が部屋に入ってきた。
「おい、あんた。ここで何してるんだ?」
「研究だが?」
「それは結構。だが今日は清掃の日だ。貼り紙見なかったのか?」
「なんだって?」男は驚いた。
慌てて部屋を出て掲示板を確認すると、清掃の日という貼り紙があった。
「さぁ、仕事の邪魔だ。どっか行っててくれ」
掃除の男に言われ、男は仕方なく研究室を出た。
ふらふらと歩いているうちに、気づくと男は花屋の前にいた。
「行ってみるか…」
店には黒髪の若い女性がいた。
「いらっしゃいませ。」
初めて見る店員だったが、美しい黒髪と表情で、彼女と一瞬見間違えた。
男がまじまじと見ていると、「私の顔に何かついていますか?」と店員の女性が微笑んだ。
「いえ、失礼。知り合いに似ていたもので…」男は答えた。「彼女に見間違えて」などと言えるはずがなかった。
「薔薇はありますか?」
「はい。赤い薔薇があります。プレゼントですか?」
「…はい。彼女に。」
店員の懐っこさについ素直に答えてしまった。
「そうだ。この赤い薔薇の花言葉を知っていますか?」
店員が男に薔薇を渡す時に言った。
「知りません。何でしょうか?」
男は聞いた。
「『告白』です。今日が…二人にとって、素敵な“記念日”になりますように。」
花屋を離れた男は、彼女に連絡を取る手段がないことに気がついた。
どうしたものかと足を止めたとき、ふと店員の妙な言い回しの言葉が蘇る。
「今日が…二人にとって、素敵な“記念日”になりますように。」
「告白…」
独りごちるように呟いた瞬間、ある光景が脳裏をよぎった。
それは、かつて彼女に告白したあの日のことだった。夕暮れの光に包まれながら、二人で並んで座ったあの場所——小高い丘の上。
男は歩き出した。あの場所に行けば、何かが変わる気がした。
丘へと続く道を登るにつれ、胸が高鳴る。もし彼女がいなかったら? もしもう、この街を出てしまっていたら?
それでも、男の足は止まらなかった。
やがて丘の上にたどり着くと、そこには——
彼女がいた。
男の足が止まる。肩で息をしながら、彼女を見つめた。
「もう会えないと思っていたのに。」
「この街を出るのか?」
彼女は静かに頷いた。
「あなたの邪魔にはなりたくないの。」
「俺は未来の俺に言われたんだ。馬鹿野郎だって。」
「……え?」
「気づいたよ。本当に俺は馬鹿だ。君を失ったら、何の意味もない。」
男は手に持っていた薔薇を差し出し、真っ直ぐに彼女を見つめる。
「俺と結婚してくれ。」
彼女は驚き、そして——泣きながら頷いた。
帰り道、彼女が微笑む。
「けど、よく薔薇を手に入れたわね。この街じゃ、今の時期、薔薇は売っていないはずよ?」
「研究室の近くの花屋で買ったんだ。」
「ふふ、今日は定休日よ?」
男は驚いた。
しかし、今日はタイムマシンで未来の自分に説教されるような日だ。花屋が定休日にやっているくらい、些細なことかもしれない。
そんな二人の姿を、遠くから見つめる男女がいた。
「うまくいったな。」掃除の男が言う。
「おじいちゃんとおばあちゃん、私たちにそっくりだったね。」
「ああ。変装して正解だった。」
男はつけ髭を外しながら言った。
「さて、これで未来は安泰だ。帰ろう。」
二人は静かに未来へと消えていった。