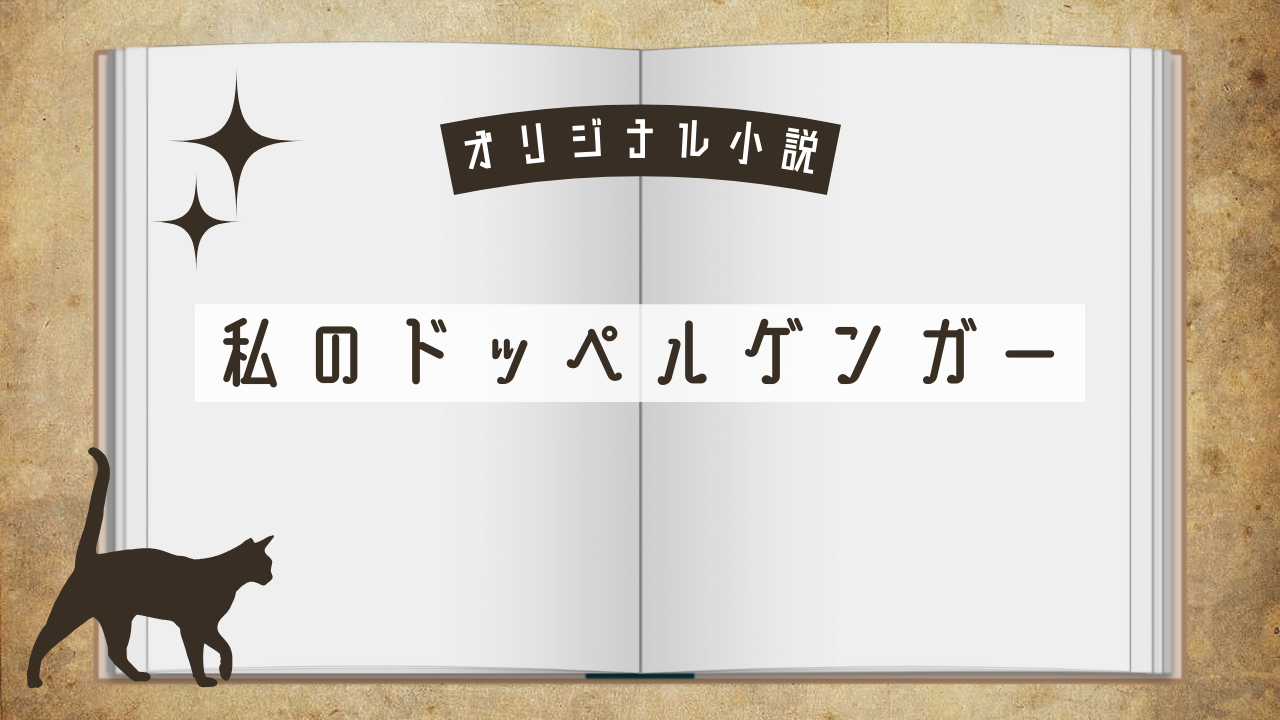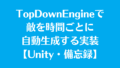「ドッペルゲンガー」と呼ばれる現象がある。
「ドッペルゲンガー」は、自分と全く同じ姿の人間を目撃するというもので、古い言い伝えでは「死の前兆」とされる。
そう。ドッペルゲンガーを見た人間は、死に至るのだ…。
なぜ私がこんな話をするのかって?それは、他でもない、私自身がそのドッペルゲンガーを目撃してしまったからだ。
****************
その日は、朝から雨が降っていた。
休日で仕事がなかった私は、お気に入りの青色の傘をさして、街へ買い物に出かけていた。ちょっとした日用雑貨を買いたかったからだ。私の服装は、動きやすい緩めのジーンズにTシャツとラフな格好で、それでも初夏の暑さで少し歩くと背中が汗ばんだ。
週末の街は多くの人で賑わっていた。
お目当てのショップにたどり着くと、店内は冷房が効いていて涼しかった。
私は、涼しい店内で、ゆったりと買い物を楽しんでいた。
その時、ふと、視界の端に何かが引っかかった。それは、何か場違いなものが見てしまったような違和感だった。
私は、ほぼ反射的に、視線を原因のある窓の外に送った。
すると、そこには私と瓜二つの人物が、青色の傘をさし、こちらを見て立っていた。
服装こそ違えど、背丈も顔も、まるで鏡に映った自分の姿をそのまま見ているかのようだった。
窓の外の人物も、私と同じように、その場で固まって驚愕の表情を浮かべている。
我に返った私が窓に駆け寄ろうとすると、「窓の外の私」は急いで踵を返し、足早に雑踏の中へと消えていった。
私は店を飛び出し、周囲を見回した。だが既に「私」の姿はどこにもなかった。雨足は、いつの間にか強くなっていた。
家に帰ってからも、私は街での出来事を反芻していた。
あれは何だったのか?
他人の空似と言うには、あまりにも自分に似すぎていた。
それに、窓の外の私がさしていた傘……。あれは、私が大切にしている青色の傘だ。もちろん、同じような傘は、探せば世の中のどこかにあるだろう。
しかし、なぜ同じ日に、同じ場所で、私と瓜二つの人が同じ傘を持っているのか、偶然にしてはあまりに出来すぎている。
私は、言いようのない恐怖に襲われた。
あれは、間違いなく「私」だった。私以外に「私」が存在したのだ。
そういえば、このような現象には名前があったはずだ…そうだ、「ドッペルゲンガー」。
まさか、心霊現象などとは無縁だと思っていた私が、ドッペルゲンガーを目撃するなんて。信じられない出来事だった。
だが、私に出来ることはない。不気味なものを感じながらも、私は普段通りの生活をすることにした。
だが、数日が過ぎたある日。仕事を終えて帰宅すると、郵便受けに見慣れない封筒が入っていた。
差出人不明の、不気味な手紙。
不思議に思いながらも封を開けた。
便箋を取り出すと、そこにはたった一行、こう書かれていた。
―――雨の日、私を見たことは、誰にも話してはいけない。警察にも、友人にも。
私は全身の血の気が引いていくのを感じた。差出人の名は書かれていなかったが、筆跡を見れば一目瞭然だった。なぜなら、それは私の筆跡と寸分違わぬものだったからだ。
「やっぱり、あれは私だったんだ」
私は、恐怖でがたがたと震えながら、郵便受けの前で呆然と立ち尽くした。
私はドッペルゲンガーの居場所も、目的も知らない。しかし、ドッペルゲンガーは私の家の場所を知っている。あの日、尾行されていた可能性も否定できない。
しかし、なぜこんなことに……?まるで、私がミステリー小説の主人公にでもなったかのようだ、と場違いにも思った。
それからというもの、私は常にドッペルゲンガーの影に怯えるようになった。どこかで監視されているのではないか、そんな疑念が常に頭から離れず、私の心を蝕んでいった。
私は、精神的に追い詰められていた。このままでは、本当に「死の前兆」が現実のものとなってしまうのではないか。そんな恐怖が、まるで影のように私を包み込んでいた。
そんな中、週末に昔からの友人とレストランで食事をする機会があった。
「ずいぶん疲れているみたいだけど。何かあったの?」
友人は、やつれた私の顔を見て、心配そうに尋ねた。
久しぶりに美味しい食事とお酒を飲み、気を許せる友人との楽しい時間。精神的に参っていた私は、友人にドッペルゲンガーのことを話すことにした。
「実はね、この前、ドッペルゲンガーを見ちゃったの」
「ドッペルゲンガーって、あの都市伝説の?」
友人は半信半疑の様子だったが、それでも私の話を疑うことはなかった。
「あなたがそんな冗談を言う人じゃないことは、私が一番よく知ってるわ。それでも、本当にそれがドッペルゲンガーだって、何か確証があるの?」
「どうやらドッペルゲンガーは、私の家の場所を知ってるみたいなの。ご丁寧に、手紙まで送ってきてくれたから」
「それは穏やかじゃないわね。」友人は赤ワインをくいっと一飲みした。
「ドッペルゲンガーに遭遇したのは、最初の雨の日の時だけ。けど、あれは間違いなく私だったわ。指してる傘まで一緒だったのよ。」
「あなたの青色の傘を?」
「ええ。」
友人は、何か考えている様子だった。
「なるほどね…。あなたが疲れている理由もわかったわ。とにかく、あなたはゆっくり休んだ方がいいわ。何かあったら、私の家においで。」
私は、友人にドッペルゲンガーのことを話せて、気持ちが楽になった。
その後も友人との食事を楽しんだ。
その夜は、久しぶりに深い眠りにつくことができた。
翌朝、玄関のチャイムの音で、私は目を覚ました。
枕元の時計を見ると、朝の8時だった。
こんな時間に誰だろう。そう思いながらドアを開けると、そこに立っていたのは―――「私」だった。
「誰にも喋るなって、忠告したのに…。」
ドッペルゲンガーは、冷たい声で言った。
「なんで…。何で、あなたが知ってるの…?」
なぜかドッペルゲンガーは昨日の出来事を知っていた。
「もう、手遅れよ」
気がつくと、私は全力で駆け出していた。
突然のことに、ドッペルゲンガーは一瞬虚を突かれたようだ。追ってくる気配はない。
私は走りながら、誰に助けを求めるべきか考えを巡らせた。
何も持たずに飛び出したため、お金も何もない。私は藁にもすがる思いで、友人の家へと向かった。
友人は家にいた。
「どうしたの!?」
友人は、息を切らした私を見て驚愕していた。
「ドッペルゲンガーが、私の家に……!」
「えっ……!?とにかく、中に入って!」
友人の家に招き入れられ、私はようやく落ち着きを取り戻し、事の顛末を説明した。
私の話を聞いた友人は言った。
友人は私と対照的に妙に冷静で、無表情に私の話を聞いていた。
「なるほどね……、しかし、その子、ルール違反だなぁ」
「ルール違反?何を言っているの?」
私の問いかけに、友人は笑いながら答えた。
「心配しないで。あなたのことは、私が”報告”しておいたから」その笑顔は、ひどく歪で、恐ろしいものに見えた。
報告…?私はその言葉を聞いて、ドッペルゲンガーが私たちの会話を知っていたこと理由に思い当たった。まさか、ドッペルゲンガーに言ったのは友人だったのか。
「もしかして、ドッペルゲンガーと繋がっているの……?」
私の言葉を聞いて、友人は、再び笑った。
「あなた、まだ分かっていないのねぇ。ドッペルゲンガーには何も言ってないよ。ただ私は、プレイヤーとして、バグを運営に報告しただけよ」
私は混乱した。目の前の友人が、まるで別人のように思えた。
その時、玄関のドアが勢いよく開かれ、一人の人物が飛び込んできた。
ドッペルゲンガーだ。
「逃げて!」
ドッペルゲンガーは私の腕を掴むと、そのまま手を引いて玄関を飛び出した。
「無駄よ!もう運営に通報済みだから!」
背後から、友人の勝ち誇ったような声が聞こえた。その声は、私を嘲笑う悪魔のようだった。
私たちは、無我夢中で走り続け、人気のない、古びた公園にたどり着いた。
「ごめんなさい。こんなことになるなら、最初からちゃんと話せばよかった」
公園のベンチに腰掛けたドッペルゲンガーは言った。
「一体どういうことなの?」
私は、息を整えながら、隣に座る”私”に問いかけた。混乱はしていたが、不思議と冷静さを保てている自分がいた。
「あなたは……私のコピーデータなの」
“彼女”は、顔を上げずに言った。その声は、悲しみの色を帯びていた。
「私が、あなたのコピー……?」
私は混乱したまま、オウム返しに尋ねるしかなかった。
「正確には、あなたは、私がこの世界をやり直す前の”私”なの」
“彼女”は、ゆっくりと顔を上げ、私を見つめた。その瞳は、悲しげな光を湛えている。
「あなたは忘れてしまっているけど…。ここは、広大なバーチャル・リアリティ・ゲームの世界なのよ」
バーチャルゲーム……? そんな馬鹿な、と私は反射的に否定しようとした。
「私は、このゲームをあるセーブ地点からやり直すことにしたのよ」
「それで、過去のデータを削除して、新しい人生を始めたの。いや、削除したつもりだった。だけど……、なぜが過去の私は消えずに、ずっと同じ生活をしていたのよ。それがあなた。」
“彼女”は再び私を見つめた。
「どうやら、ゲームのバグで過去のデータが完全に消去されず、この世界に残ってしまっていたみたい。そして、そのデータが実体化し、意思を持って動き出してしまった。それがあなたよ。本来、私たちは同時に存在してはいけない。それは、ゲームの重大なバグだから。この世界の運営にこの事実が知られたら、バグであるあなたは、強制的に削除されてしまう」
「でも、あなたを見た時、どうしてもあなたを削除させたくないと思ったの」
“彼女”は、青色の傘をどこかから取り出した。
「この傘、私がこのゲームを始める時に、最後に設定したアバターアイテムで限定品だったの。とても大切なものなの」
“彼女”は、微笑んだ。
「あなたがその傘を大切にしているの見て……あなたも、やっぱり私なんだって、そう感じたの。それで……あなたを守らなきゃって、そう思って手紙を送ったのよ」
“彼女”は、そこで言葉を切り、悔しそうに唇を噛んだ。
「けどあなたは友人に話してしまった。友人は、私と同じゲームのプレイヤーだったのよ。だから友人は、運営に報告したのよ。友人は、あなたがバグだと気づいてしまったら」
「そんな……、嘘よ……」
信じられない話だった。しかし、”彼女”の真剣な表情が、これが真実なのだと告げている。
「ごめんなさい……」
“彼女”は、再び謝罪の言葉を口にした。
私は、全身から力が抜けていくのを感じ、その場にへたり込んだ。
頭がぼんやりとしてきた。まるで、電源が落ちる寸前のコンピューターのように、思考がゆっくりと停止していく。
「そうか……、私の方が、ドッペルゲンガーだったんだ……」
ドッペルゲンガーを見ると死ぬ予兆というが、死ぬ方がドッペルゲンガー側だったのかもしれない。そんなことを思いながら、私というデータは消えていった。